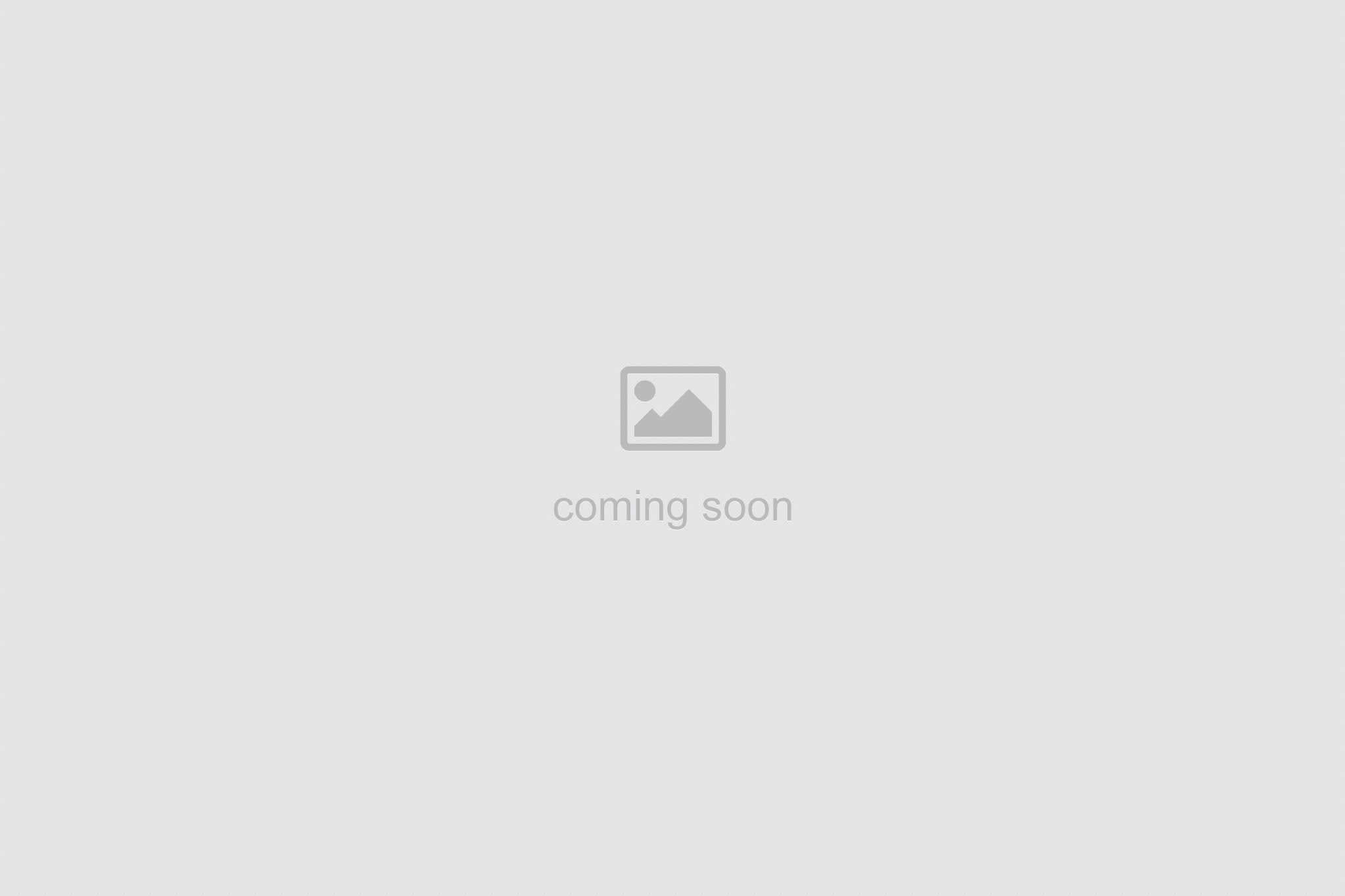「気付き」から「動き」へ・ヒヤリハットの現場から
2025-04-06
カテゴリ:社会福祉に関すること
注目NEW
こんにちは、統括施設長の田原です。
ついに発売から後10日と迫った
布袋寅泰最新アルバムGUITARHYTHM Ⅷ!!
前作、GⅦが私的にはドはまりしたアルバムだったので期待は高まるばかり。
今度はどんな冒険となるのか。
到着が待ち遠しいところです。
それでは「ひこぶろ」社会福祉に関することの1発目をお送り致します。
先日ネット記事である知的障がい者施設を糾弾する記事がありました。
何でもその施設では利用者が職員へ性的不適切な発言などをすると反省文を書かせたり
懲罰として買い物を制限したりしているそうです。
私は高齢分野での勤務経験しかないので、このような対応が知的障がい者施設の
スタンダードなのかは知りませんが
一般的な感覚では異常と感じてしまうのは私だけでしょうか。
もちろん性的不適切な発言を容認する必要はありません。
しかし知的障害という判断能力に課題のある方の支援をする場合
そのような発言が何故良くないのかをしっかり説明する事も支援の一つでしょう。
例え何回説明しても同じ事を繰り返したとしても何回でも説明すべきです。
その説明が反省文という形ならならまだ理解も出来るかも知れませんが
(私は到底理解も納得でも出来ませんが)
買い物の制限などの懲罰的な事をする必要は全くないでしょう。
これが虐待と即なるのかは保険者判断ですが
少なくとも権利侵害である事は明々白々な事実です。
この記事に書かれてある不適切な対応に関する疑問には基本的に全て同意します。
しかし一点どうしても納得出来ない記述がありました。
それは以下の点です。
【T作業所ではこのパターナリズムが蔓延していた。
利用者に関する「ヒヤリハット」や「事故報告書」の記載をやたらとパート職員に
要求したのもその1つの顕れだったかもしれない。
「ヒヤリハット」とは事故や災害を被る一歩手前の状況に遭遇し
「ヒヤリ」とさせられた案件報告。「事故報告書」は文字通り事故が発生したときの
案件報告だが取るに足りない些細な案件までもこれらに組み入れることで
利用者たちに対する監視の目と制約は当然ながら強化される。】
まぁこの記事の本質はここではありませんし
それこそ切り取り、揚げ足取りと批判されるかも知れませんが
それでもネットニュースという不特定多数の方が目にする記事で
この表現は好ましくないと言わざるを得ないでしょう。
事故報告書の過剰な要求は確かに不適切かも知れません。
しかしヒヤリハットは別でしょう。
ヒヤリハットは「気付き」を促す物です。
いくらそれを書くように要求しても、それは「気付きの視点」
つまり「観察眼」を養う目的で行うのであって、決して監視の目と制約を強化する等の
目的ではありません。
これではヒヤリハットをたくさん書いている施設が監視社会を作りたいと
勘違いしてしまう人がいるかも知れません。
もちろん、この記事の本筋はここではないのですが
それでもネット記事で誤解を与えるような記述は不適切でしょう。
以前の記事でも述べた事ですが
当施設では、職員一人一人に月1回ヒヤリハットの提出を義務付けています。
ヒヤリハットはハインリッヒの法則に基づいたものであり
何もこの介護・福祉業界に特化したものではなく
全ての業種に採用されているものです。
この法則によると1件の重大な事故の下に29件の軽微な事故があり
さらにその下に300件のヒヤリハットがあるというものです。
つまり重大、軽微含め、事故の10倍はヒヤリハットがあるという事になります。
当施設では毎月平均5~10件ほどの事故報告書が提出されています。
という事はハインリッヒの法則に従えば
当施設には毎月50~100件のヒヤリハットがある事となります。
当施設の居室数は小規模多機能を含め49室です。
つまり小規模多機の通い利用者を含めると
大体50人以上は毎月利用して頂いている事となります。
そして職員も大体50人ぐらいです。このような人数であれば
毎月一人1ケースぐらいヒヤリハットの「気付き」があってもおかしくないというのが
この取り組みのエビデンスです。
そんな訳で私は毎月膨大な量のヒヤリハットに目を通すのですが
折角「気付いて」いるのに勿体ないなぁと思うケースもあります。
居室内での自身でのふらつきや急な膝折れなど
何回ヒヤリハットを経験しても不可避なケースもあります。
しかし中には対策さえしておけば防げるケースもあります。
防げるケースの最もポピュラーなものは服薬に関するケースでしょう。
それも一度口に含んだ薬剤を利用者自身が吐き出すなど防ぎようのないような
ケースもありますが、服薬忘れや薬剤のセットミスは少しの注意で防げるものに
分類されるでしょう。
しかしそうは言ってもヒューマンエラーは絶対に起こるので仕方のない場合もあります。
そんな中でも残念だなぁと思うケースが先月ありました。
それはフロアの机の上に置いてあったティッシュを口に含んでいた(含みそうになった)
というケースでした。
これが残念に思ったのは1回目が起こった2日後に同じ利用者で同じように
ティッシュを口に含んでしまっていた事でした。
この場合は折角1回目に「気付けた」のだから、その日のうちにティッシュを机から
移動させるなどの対策を講じていれば2回目は防げた可能性が高いです。
つまり現場を目撃した「気付き」から
実際にティッシュを移動させる「動き」に移行出来ていなかったのです。
もちろんティッシュの使用も利用者の権利なので
何でもかんでも撤去すれば良いと安易に考えるべきではありません。
しかし危険だとわかっているのにそのまま放置するのは権利擁護でも何でもなく
逆に広義の意味では放任の虐待と言えなくもありません。
(もちろん意図的に放置した場合のみですが)
このような場合はご自分では触れない位置に置く
蓋つきの箱に入れるなどの対応は全くもって正当な対応と言えます。
もちろん緊急時を除き一人の職員の判断で実行するのは権利擁護の観点から
不適切なので、複数の職員で検討する事が必要なのは言うまでもありませんし
ケースによっては身体拘束廃止・適正化委員会の開催も必要になってくるでしょう。
このように折角ヒヤリハットで「気付い」てもその後に「動き」がなければ折角の
ヒヤリハットのただの紙くずになってしまう結果となります。
皆さんの折角の「気付き」を無駄にせず事故を未然に防ぐためにも
是非「気付き」から「動き」への移行を意識して頂きたいと思います。